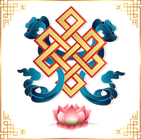諸法非我(しょほうひが)

つぎは「諸法非我」(しょほうひが)である。直訳では、あらゆるモノゴトは「本質」ではない、という意味である。仏教における核心的教義であろう。三法印(四法印)の中では最も理解が難しい。
ここで「本質」は、実体と言い換えることもできる。「あるときは〇〇、またあるときは××、しかしてその実体は△△」というキャッチフレーズがあるが、時と場合によって〇〇や××に変化しても、決して変化することのない△△が本質である。絶対性・固定性・自立性をもつ実体、簡単にいえば「決して変化しないもの」のことである。あらゆるモノゴトは不変の実体ではない、というのが非我である。
先に「諸行無常」でいう変化を認識できるのは変化しないものについてであると述べた。では 変化しないものは存在するのか。これさえも否定するのが「諸法非我」の教えであり、「無常」(時間的に変化しないものはない)と「非我」(空間的・概念的に変化しないものもない)とがワンセットとなって「空」と同義となる。
古代インドでは、宇宙や世界を含む物質・概念(=認識対象)の本質を「ブラフマン」と呼び、これに対して私(=認識主体)の本質を「アートマン」と呼んで区別した。ブラフマンの漢訳が「梵」で、アートマンの漢訳が「我」である。人についていえば、さしずめ「梵」=肉体、「我」=魂ということになろう。そして、「私」の本質として決して変化しない魂が、生まれる前から有り、肉体が死んだ後も残るというアイデアが物語性を帯び、魂が次々に肉体を得て生まれ変わり死に変わりするところの輪廻(転生)説となったのである。当時、その生老病死の苦しみから永久に解脱するためには、修行を重ねて梵我一如(認識対象と認識主体の区別、人体でいえば肉体と魂の区別が消失した境地)に至る必要があるとされた。
しかし、当時の大衆のほとんどはこの梵我一如論を誤解して受け取った。 認識主体は決して認識対象にはなり得ないから、肉体は認識できても魂なるものは決して認識できない。それなのに、 我を実体視してしまい、魂のみが実在であって肉体は幻であると逆に捉え、肉体の苦痛を感じなくなる境地(いわば肉体の消失)こそが梵我一如であると思い込み、その境地に近づくために必要であると誤解して、こぞって「苦行」を始めたのである。死をも恐れぬ修行こそがその境地に近づいていることのバロメータとされた。
釈尊も、当初はそのように流行していた苦行を主とする修行者の一人であったが、自らの体験をもって梵我一如の境地を正しく悟った後、大衆の誤解をただすため、あえて我を強く否定し、「あなた方が我であると思っているものは決して我ではない(我に非ず)」と説いた。それが諸法非我の教えである。決して認識対象となることのない我は、〇〇であると本質的に定義できるようなものではない(非我)、ということである。
よって、一般に釈尊は伝統的な古代インド哲学の梵我一如論に反旗を翻して新たに仏教を説いたといわれるが、方法論の違いに過ぎず、究極的には両者は同じ哲学である。すなわち、梵我一如の境地に至った場合は梵と我の区別自体が消失するのであるから、すべては梵であるともいえるし、すべては我であるともいえる。すべてが梵であるなら我を持ち出す余地がないし、すべてが我であるなら我と我以外を区別する「我」という概念自体が意味を持たない。すなわち梵我一如=非我である。
このように、一般に釈尊は「無我」を説いたといわれるが、正確には「非我」を説いて、衆生を正しい梵我一如論に導いたのである。人体でいうところの我すなわち魂の存在については、有るとも無いとも断定せず、「無記」(むき)という判断保留の態度を貫いた。認識対象となり得ないのであるから、当然の帰結である。従って、釈尊は魂が「無い」とは断定しておらず、わかる方法がないとしているのみであるから、非我を説く釈尊が輪廻説を否定しなかったとしても、また方便として輪廻を説いたとしても、何の不思議もない。そもそも諸法非我や空と輪廻説はしないのである。