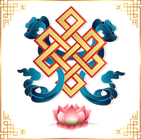無記(むき)
釈尊は、下記のような人間の経験を超越する形而上の問いには答えなかったとされる。西洋哲学でいうエポケー(判断停止) の態度である。 単に答えが出ない問いであるが故の単なる沈黙ではない。今ここにある苦悩の原因を滅却するための実践を説く仏教において、 かりに答えたとしても 何ら解決の役に立たない問いに拘泥し、迷い続けて虚しく時を過ごすことを戒める一つの教えである(毒矢のたとえ)。さらに言えば、むしろ迷いを深めさせてしまうが故の、答えてはいけない問いなのである。
1.世界は永遠であるのか
2 世界は永遠でないのか
3 世界は有限であるのか
4 世界は無限であるのか
5 霊魂と身体は同一か
6 霊魂と身体は別個か
7 如来は死後に有るのか
8 如来は死後に無いのか
9 如来は死後に有りながら無いのか
10 如来は死後に有るでもなく無いでもないのか
まず、答えが出ない問いであるとはどういうことか。
「世界」は仏教用語である。「世」は時間のひろがりを、「界」は空間のひろがりをいう。例えば、仏教で「三世」(さんぜ)といえば「前世」「現世」「来世」の3つを指し、「三界」(さんがい)といえば「無色界(天上界の最上層=有頂天)」「色界(天上界の中層)」「欲界(天上界の最下層から人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界まで)」の3つを指す。要するに「時空」のことである。
従って、1と2は時間に終わり(終末)はあるか否か、という問いであり、3と4は空間に終わり(果て)はあるか否か、という問いになる。
時間に終わり(終末)はあるか否かであるが、そもそも時間とは変化の影である。AからBに変化することの裏返しとして、Aである時とBである時の間に流れ(時間)があったものと推論しているに過ぎない。 つまり、何も変化しなければ時間という概念は成り立たない。 従い、時間に終わり(終末)があるなら、終わった後は何も変化しない。逆に時間に終わり(終末)がないなら、始まりもないから、変化が止まるという事態が想定できない。つまり、すべては無始無終で変化し続けるのか、それとも変化が止まる事態はあるのか、という問いにある。いずれも概念(言葉)では言えるが、経験はおろか観念(思い描く)こともできない。円い三角とは何かという問いと同じである。もはや問い自体が人間にとっては成立しないのである。
空間に終わり(果て)があるか否かという問いも、同様に問い自体が人間にとっては成立しない疑似問題である。空間に終わり(果て)があるなら、空間ではない向こう側というものもなければならない。空間に終わり(果て)がないなら、 すべてが空間であることになる。つまり、空間ではない異次元があるのかどうか、という問いである。これまた概念(言葉)ではいえるが、経験はおろか観念する(思い描く)こともできない。これも円い三角とは何かという問いと同じである。人間にとって答えを出しうる問いではない。
5と6は霊魂と身体を区別できるかという問いである。物質である身体は「梵」に属し、非物質である霊魂は「我」に相当する。仏教以前のインド哲学(ウパニシャッド)の教義では「梵我一如になる」ことを目指して修行するものとされ、前提として常態では身体と霊魂は別個独立の実体とされていた。釈尊は固定不変の実体としての我を認めない非我の立場から、「もともと梵我一如である」ことを悟るのが修行であるとした。そうすると、身体と霊魂という区別自体がない前提であるから、同一であるか別個であるかという問い自体が成立しないことになる。ちなみに、これは死後の世界があるかどうかという問いではない。同一であればもとより、別個であっても同時に消滅するなら、いずれにせよ死後の世界はないことになるから、これを釈尊が輪廻を否定した根拠とするのは間違いである。
7以降は如来の死後の存在を問うものであるが、あくまで修行完成者(最終解脱者)の死後を問うものであり、釈尊自身がまだ死んだことがないのであるから、この問いに答えられるわけもない。釈尊は如来ではあっても人間釈迦なのである。
次に、答えを出しても何ら解決に役立たない問いであるというのはどういうことか。
それは、なぜ釈尊は自身の言葉を文字で残さなかったのかを考えればわかる。釈尊は自ら書いたものも、弟子たちに書かせたものも残されていないという。もちろん当時、文字や書がなかったわけではない。古代インドではインダス文字の流れをくむブラーフミー文字が紀元前1000年ころ使われていた。紀元前500年ころの釈尊時代より前からである。釈尊らは雨安居(うあんご)の時期(雨季)を除いて各地を巡教しており、そもそも筆記用具など持ち歩く状況になかったのであろうが、むしろ文字に残さない積極的理由があったように思えてならない。すなわち、文字にすると意味がなくなる、あるいは文字で残すとかえって迷わせる、という考慮があったのではないであろうか。達磨大師が経典のひとつもインドから中国に持ち込まなかったこと、道元禅師が経典のひとつも中国から日本に持ち帰らなかったことも、同じ文脈で理解できる。すなわち、不立文字(ふりゅうもんじ)である。ただ、禅語では「仏法は文字にできるものではない」という意味になるが、釈尊の生きた時代では「仏法は文字にすべきものではない」という意味であったろうと思われる。
というのも、釈尊らの説法は、釈尊自身が「私にはこれを説くということがない」というとおり、同じ内容の教えであっても、型にはまった同じ方法で一方的に説くのでなく、相手の状況や受け答えに応じて柔軟に、ときには比喩や方便を交えて全く違う語り方で、というものであった。これを対機説法という。つまり、その場にいない者は説教の相手にしていないのである。それは何故か。インタラクティブな体験を伴う言葉による対話と異なり、そのような体験を伴わない言葉のみによる文字では、仏法を間違って受け取られるおそれがある、従って文字にすべきものではないのである。
とすれば、釈尊の入滅後に、高弟たちが結集して仏典の編纂に走ったのは、もっぱら遺された側の事情によるものであり、いわゆる原始経典であれ大乗経典であれ、釈尊の意図がそのまま表れている保証がないどころか、編纂されたこと自体が釈尊の意に反しているといっても過言ではなくなる。ましてや一部の大乗経典において、釈尊に神格を付与したり、超能力を創造したりして話を盛るのは、釈尊の意図とは真逆であるというべきである。後の世に新興宗教の開祖として祭り上げられているとは夢にも思わなかったに違いない。
要するに、かりに答えようと思えば答えを出せたとしても、体験を伴いようがない形而上の問いには、答えることでかえって相手を迷わせる以外の何ものにもならないと、釈尊は考えたはずである。